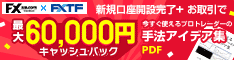先行き不安からドル調達の動きに
「とにかく今はドルを確保することが優先」「ドル不足に落ち込むことが一番の懸念材料」。新型コロナウイルスの感染が欧米へと拡大し始めた直後、グローバルに事業展開している日本企業の経営者から「ドルを調達できなくなることへの不安」を度々耳にするようになりました。
金融機関はもちろん、海外でビジネスを行っている日本企業も、ドルを中心とした外貨建てで取引を行うため、数か月先までの外貨を予約したり、一部を手元に準備したりしています。5や10のつく「五十日(ゴトー日)」の朝9時55分前、仲値が決まる時間帯にドルの取引が活発になるのは、多くの企業がゴトー日に決済をしていて、その決済のための資金を銀行が準備しているためだといわれています。
ただ、“実需筋”の取引が為替取引全体に占める割合は1割程度と少なく、ゴトー日や仲値、年末、年度末の特徴的な動きが注目されるだけで、一般的には残りの9割を占めるヘッジファンドなど“投機筋”の動きが重視されがちです。しかし、ショック時は別です。多くの人がトイレットペーパーを買い急いだように、実需筋が経済悪化の長期化に備えて一斉にドル買いに動いた結果、ドルの調達コストは100年に一度の金融危機といわれたリーマン・ショック以来の水準まで急上昇しました。
3月9日に一時101円台まで下落していたドル円相場がみるみるうちに上昇し、たった一週間程度でコロナショックでの下落分を帳消しにしたあの動きは、実需筋の動揺が発端だったのでしょう。動揺を抑え、「いつでもドルが手に入る安心感」を与えるために、米連邦準備制度理事会(FRB)は緊急利下げを行わざるを得ず、欧州中央銀行(ECB)や日銀などの中央銀行も協調してドル資金の供給に踏み切ったのです。
さかのぼれば、2008年に起きたリーマン・ショックのときも、ドル円は90円台まで下落した後、いったん100円台まで上昇しました。しかし、中銀が協調利下げを行った後、ドル円相場は一転して、2011年10月に75円台半ばをつけるまでの3年間にわたり、超円高ドル安のトレンドが継続しました。
今回の新型コロナウイルスは、金融のみならず多くの人々を動揺させ、安全を奪いました。世界を安心させるためには、より長い時間が必要なのかもしれません。
※この記事は、FX攻略.com2020年6月号の記事を転載・再編集したものです。本文で書かれている相場情報は現在の相場とは異なりますのでご注意ください。

「これからFXを始めよう」と思ったとき、意外と悩んでしまうのがFX会社、取引口座選びではないでしょうか? でも大丈夫。ご安心ください。先輩トレーダー達も最初は初心者。みんなが同じ悩みを通ってきているんです。
10年以上にわたってFX月刊誌を出版してきた老舗FXメディア「FX攻略.com」編集部が、FX用語を知らない人でもわかるようにFX会社、取引口座のポイントを解説しました!
取り上げているFX会社は、金融商品取引業の登録をしている国内FX業者です。口座開設は基本的に無料ですので、まずは気になったところで2〜3つ口座開設してみて、実際に比べてみてはいかがでしょうか。
\FX会社によって違うところをチェック/
| スプレッド | FX取引における取引コスト。狭いほうが望ましい。 |
|---|---|
| 約定力 | 狙った価格で注文が通りやすいかどうか。 |
| スワップポイント | 高水準かどうか。高金利通貨の取り扱いの数。 |
| 取引単位 | 少額取引ができるかどうか。運用資金が少ないなら要チェック。 |
| 取引ツール | 提供されるPC・スマホ取引ツールの使いやすさ。MT4ができるかどうか。オリジナルの分析ツールの有無。 |
| シストレ・自動売買 | 裁量取引とは別に自動売買のサービスがあるかどうか。 |
| サポート体制 | サポート内容や対応可能時間の違いをチェック。 |
| 教育コンテンツ | 配信されるマーケット情報や投資家向けコンテンツの有無。 |
| キャンペーン | 新規口座開設時や口座利用者向け各種キャンペーンの内容。 |
![FX攻略.com[公式]FX初心者入門と為替情報が満載!](https://fx-koryaku.com/wp-content/uploads/2021/02/logo-white-big-1.png)



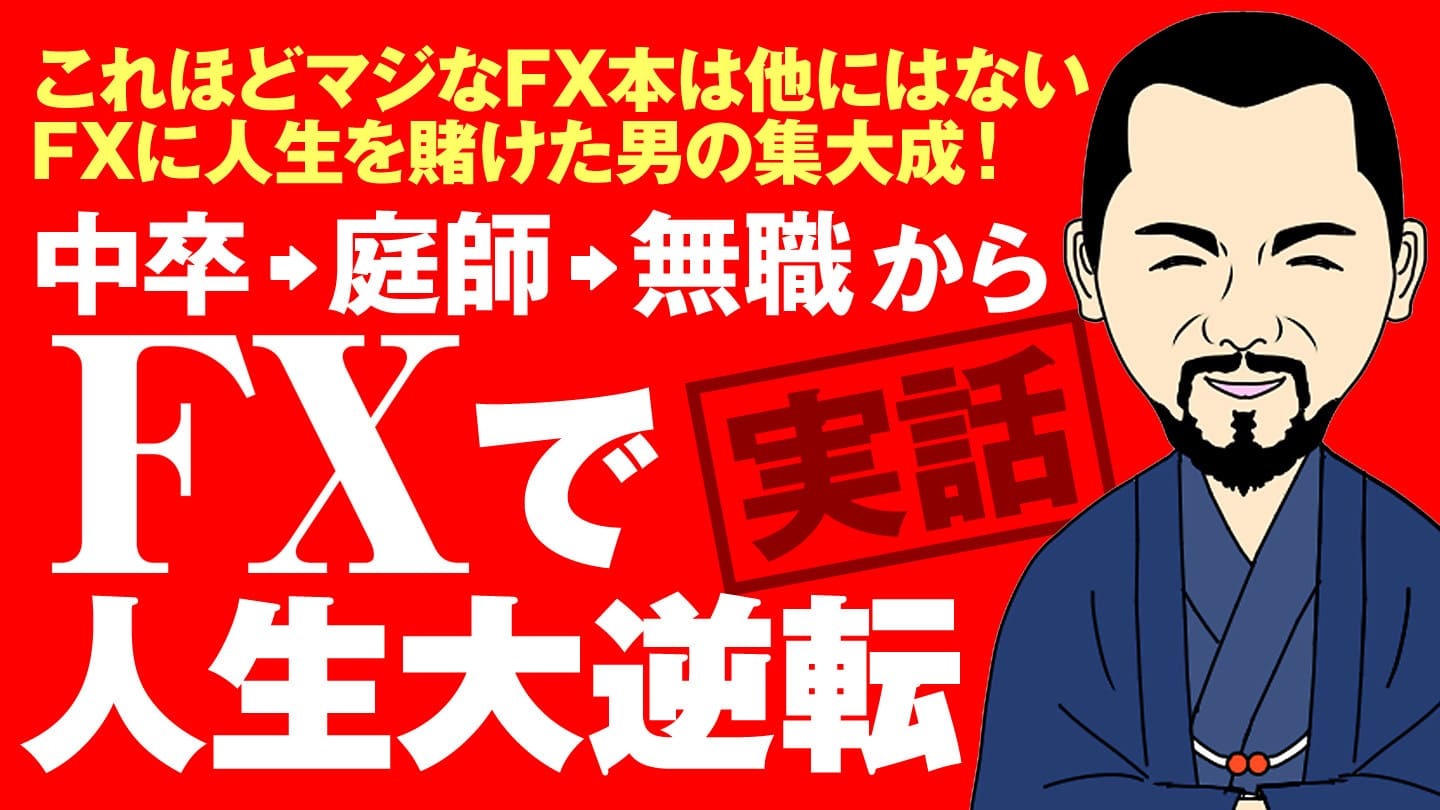 \新刊/『岡ちゃんマン流FXトレードのすすめ』 Kindleストアで好評発売中!!
\新刊/『岡ちゃんマン流FXトレードのすすめ』 Kindleストアで好評発売中!!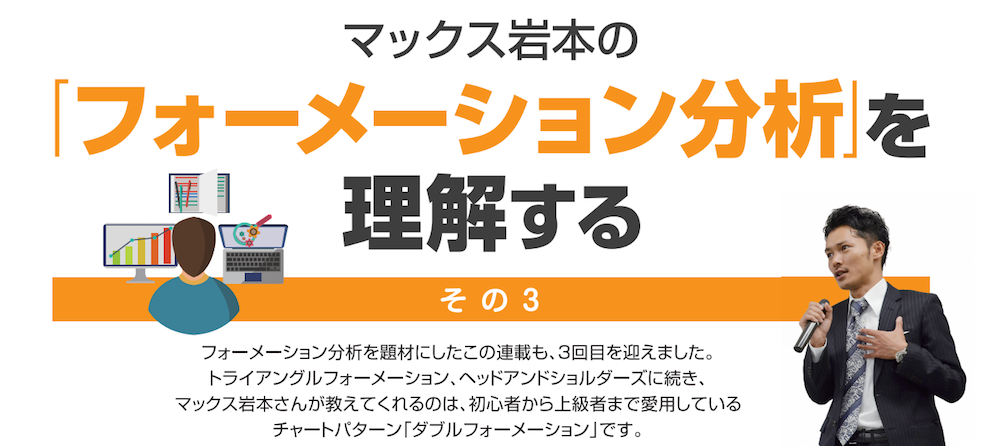


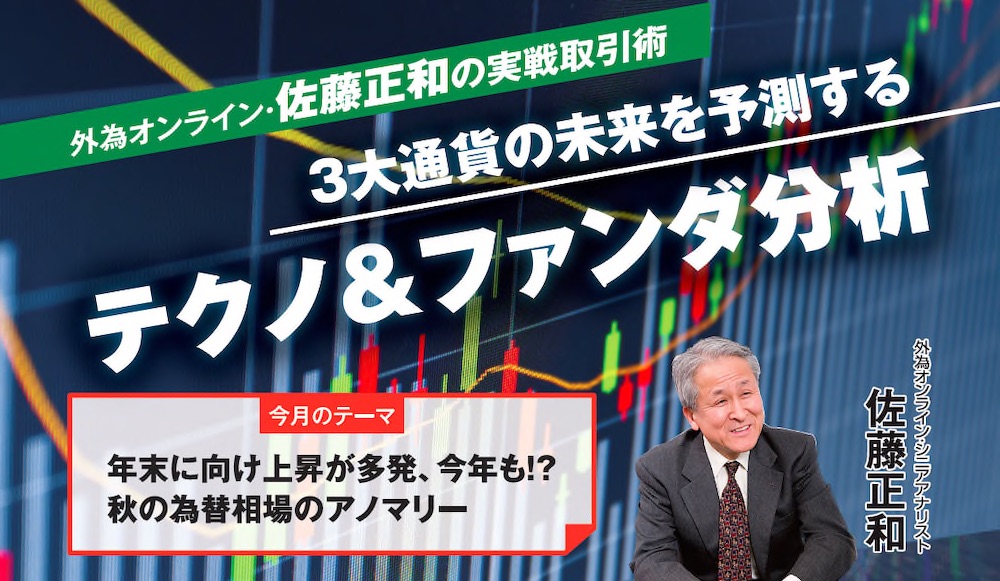

![コロナ感染再拡大と株安でリスク回避強まる[雨夜恒一郎]](https://fx-koryaku.com/wp-content/uploads/2020/09/amaya-20200928-0.jpg)

![現役為替ディーラーが、話題のアノ人と語り尽くす Trader’s対談|ゲスト YEN蔵 後編[トレイダーズ証券みんなのFX 井口喜雄]](https://fx-koryaku.com/wp-content/uploads/2020/06/traders-iguchi-202005-1.png)
 \世界一やさしい自動売買シストレ作成ソフト/
\世界一やさしい自動売買シストレ作成ソフト/ \新刊/岡ちゃんマン流FXトレードのすすめ
\新刊/岡ちゃんマン流FXトレードのすすめ